承知いたしました。中小企業診断士試験の「経済学・経済政策」について、大学生にも理解できるよう、各項目をさらに深掘りして解説します。経済学は一見すると複雑な数式やグラフが多くて難しそうですが、身近な生活やニュースと結びつけると、非常に面白い学問です。
ミクロ経済学:私たちの選択と市場のメカニズム
ミクロ経済学は、私たち消費者や企業といった、経済社会を構成する最小単位のプレーヤーが、どのように考え、行動するのかを分析する分野です。「ミクロ(Micro)」が「小さい」を意味する通り、個々の木に注目するイメージです。
1. 消費者行動理論:あなたはどうやって買い物を決める?
これは「消費者が、限られたお小遣いの中で、どうすれば一番ハッピー(満足)になれるか?」を科学する分野です。
キーワード:効用、無差別曲線、予算制約線
- 効用: 商品やサービスを手に入れたときの「満足度」や「うれしさ」のことです。
- 予算制約線: あなたが使えるお金(予算)で、買える商品の組み合わせの上限を示した線です。例えば、1000円のお小遣いで、100円のジュースと150円のサンドイッチを何本・何個ずつ買えるか、という組み合わせのラインです。
- 無差別曲線: 「ジュース5本とサンドイッチ2個の満足度」と「ジュース2本とサンドイッチ4個の満足度」が同じ、といったように、あなたにとって満足度が等しくなる商品の組み合わせを結んだ曲線です。この線上なら「どれを選んでもハッピー度は同じ」なので「無差別」という名前がついています。
どうやって最適な選択をするのか?
消費者は、自分の「予算制約線」と、できるだけ外側にある(満足度が高い)「無差別曲線」が、ちょうど接する点(最適消費点)で商品を購入するとき、満足度が最大になると考えます。これは、限られた予算内で、最もハッピーになれる買い物の仕方を見つけるプロセスを理論化したものです。
キーワード:需要の価格弾力性
これは「商品の値段が1%下がったときに、需要(売れる量)が何%増えるか?」を示す指標です。
- 弾力性が大きい(弾力的): 値下げすると、売れ行きが大きく伸びる商品。例えば、高級ブランドのバッグや宝飾品など、贅沢品がこれにあたります。セールになると、普段は買わない人も「今がチャンス!」と購入します。
- 弾力性が小さい(非弾力的): 値下げしても、売れ行きがあまり変わらない商品。例えば、トイレットペーパーや塩、醤油などの生活必需品です。安くなっても、買いだめする量には限界があります。
企業は、この弾力性を考えて「この商品は値下げすべきか、値上げしても大丈夫か」という価格戦略を立てています。
2. 生産者行動理論:会社はどうやって利益を出す?
これは「企業が、どうすれば利益を最大にできるか?」を分析する分野です。
キーワード:生産関数、費用関数、限界費用
- 生産関数: 従業員(労働)や機械設備(資本)をどれだけ投入すれば、どれだけの製品を作れるか(生産量)を表す関係式です。
- 費用関数: 製品を生産するのにかかるコスト(費用)が、生産量に応じてどう変わるかを示します。人件費や材料費、家賃などが含まれます。
- 限界費用: 「製品をもう1個追加で生産するときにかかる追加コスト」のことです。これが非常に重要な概念です。最初は生産量を増やすと効率が良くなり限界費用は下がりますが、ある点を超えると、工場が手狭になったりして逆に非効率になり、限界費用は上がっていきます(U字型のカーブを描きます)。
利益が最大になるのはいつ?
企業は「限界収入(もう1個売ったときの収入)= 限界費用(もう1個作るときのコスト)」となるときに、利益が最大になります。
なぜなら、限界収入が限界費用を上回っているうちは、作れば作るほど儲けが増えるので、もっと生産すべきだからです。逆に、限界費用が限界収入を上回ってしまうと、作れば作るほど赤字になるので生産を減らすべきです。そのちょうど境目となる点が、利益が最大になる生産量なのです。
3. 市場理論:モノの値段はどうやって決まる?
消費者と生産者の行動が集まる「市場」で、商品の価格と取引量がどのように決まるのかを分析します。市場の競争の激しさによって、いくつかのタイプに分かれます。
- 完全競争市場: 売り手も買い手も非常にたくさんいて、誰も価格をコントロールできない市場。例えば、野菜や魚などの農水産物市場が近いイメージです。個々の農家がキャベツの値段を勝手に決めることはできず、市場全体の需要と供給のバランスで価格(市場価格)が決まります。この市場では、社会全体の満足度(総余剰)が最も大きくなり、経済学的には理想の状態とされます。
- 独占市場: 売り手が1社しかいない市場。例えば、地域独占の電力会社や水道事業がこれにあたります。ライバルがいないため、企業は利益を最大化するために、価格を高く設定し、生産量を少なくする傾向があります。そのため、完全競争市場に比べて社会全体の満足度は下がってしまいます。
- 寡占市場: 2〜数社の巨大企業が市場を支配している状態。携帯電話キャリア、ビール業界、自動車業界などが典型例です。お互いに相手の出方(値下げ、新商品投入など)を強く意識しながら価格や戦略を決めるため、「ゲーム理論」という手法で分析されます。相手の戦略を読み、自分の利益が最大になるような行動(最適反応)を考える、さながらチェスや将棋のような世界です。
4. 市場の失敗:市場に任せるとマズいこと
市場メカニズムは万能ではなく、うまく機能しない場合があります。これを「市場の失敗」と呼び、政府が介入する根拠となります。
- 外部性: ある人の行動が、取引とは無関係な第三者に意図せず影響を与えてしまうことです。
- 外部不経済(悪い影響): 工場が汚染物質を川に流す「公害」が典型例です。工場はコストを払わずに環境を汚し、地域住民の健康が害されます。この場合、政府は汚染物質に税金(ピグー税)を課すことで、企業に社会的コストを負担させ、問題を解決しようとします。
- 外部経済(良い影響): ある果樹園の隣で養蜂家がハチミツを作り始めたとします。ミツバチは果樹園の受粉を手伝い、果物の収穫量が増えます。一方、ミツバチは果物の蜜を集めることができます。お互いに良い影響を与え合っていますが、そのことでお金のやり取りは発生しません。
- 公共財: 警察、消防、国防、公園など、以下の2つの性質を持つサービスや財のことです。
- 非排除性: お金を払わない人を、そのサービスの利用から排除することができない(例:タダで公園を利用できる)。
- 非競合性: 誰かが利用しても、他の人が利用できる量が減らない(例:誰かが警察に守られても、他の人が守られなくなるわけではない)。
この性質のため、民間企業が提供すると「タダ乗り」する人ばかりで儲からないため、誰も供給しなくなります。そのため、政府が税金を使って提供する必要があるのです。
- 情報の非対称性: 売り手と買い手の持っている情報に大きな差がある状態です。
- 逆選択: 情報を持たない側が、望まない相手を選んでしまうこと。中古車市場が有名で、買い手は車の本当の品質(情報)が分からないため、故障しやすい「レモン」と呼ばれるような質の悪い車を買ってしまうリスクを恐れます。その結果、良質な車は正当に評価されず市場から消え、質の悪い車ばかりが出回ってしまう現象が起きます。
- モラルハザード: 情報を隠して行動できる側が、自分に都合のいいように行動してしまうこと。例えば、自動車保険に入った人が「どうせ保険が下りるから」と安心して、運転が荒っぽくなるようなケースです。
マクロ経済学:国全体の経済の大きな流れを読む
マクロ経済学は、GDP、物価、失業率といった国全体の経済指標に注目し、経済の大きな動きや、政府・日本銀行の政策がどう影響するのかを分析します。「マクロ(Macro)」が「大きい」を意味する通り、森全体を眺めるイメージです。
1. 国民経済計算:国の健康診断「GDP」
- GDP(国内総生産): 「1年間に、日本国内で新たに生み出されたモノやサービスの付加価値の合計額」のことです。国の経済規模や景気の良し悪しを示す、最も基本的な指標です。
- 三面等価の原則: GDPは、「生産(何が作られたか)」「分配(誰の所得になったか)」「支出(何に使われたか)」という3つの異なる側面から計算できますが、その合計額は必ず一致するという原則です。ケーキ屋さんの例で考えると、「①お店がケーキを作る(生産)」→「②作った分が店主の儲けや店員の給料になる(分配)」→「③そのお金でお客さんがケーキを買う(支出)」という一連の流れで、お金がぐるぐる回っているイメージです。
2. 財市場の分析(IS曲線):モノやサービスの市場
国全体のモノやサービスがどれだけ必要とされ(需要)、どれだけ作られるか(供給)を分析します。
- 乗数効果: 政府が公共事業で1兆円使うとします。そのお金はまず建設会社に渡ります。すると、建設会社は儲かり、従業員の給料が増えたり、新たな機械を買ったりします。給料が増えた従業員は、そのお金で買い物をします。買い物されたお店もまた儲かり…というように、最初の一撃(1兆円)が、次々と経済全体に波及していき、最終的には1兆円以上の経済効果を生み出します。この波及効果を「乗数効果」と呼びます。
- IS曲線: 「モノやサービスの市場(財市場)が均衡する(需要=供給)、国民所得と利子率の組み合わせ」を示した、右下がりの曲線です。
- なぜ右下がり? → 利子率が下がると、企業は銀行からお金を借りて工場を建てたり(設備投資)、個人はローンで家や車を買ったりしやすくなります。その結果、モノやサービスへの需要が増え、経済が活性化し、国民所得が増えるからです。
3. 貨幣市場・資産市場の分析(LM曲線):お金の市場
世の中に出回っているお金の量(供給)と、人々が手元に持っていたいと思うお金の量(需要)の関係を分析します。
- 貨幣需要: 人々が現金や預金を持ちたがる理由は、①日々の買い物に使うため(取引動機)、②将来の不測の事態に備えるため(予備的動機)、③有利なときに株などを買うため(投機的動機)の3つがあります。利子率が高いと、現金で持っているより銀行に預けた方がお得なので、貨幣需要は減ります。
- LM曲線: 「お金の市場(貨幣市場)が均衡する(需要=供給)、国民所得と利子率の組み合わせ」を示した、右上がりの曲線です。
- なぜ右上がり? → 国民所得が増えると、人々の給料が増え、買い物も増えるので、手元に置いておきたいお金の量(貨幣需要)が増えます。一方、お金の供給量(日銀がコントロール)は一定なので、皆がお金を欲しがる結果、お金を借りるためのコストである利子率が上昇します。
4. IS-LM分析:経済政策の効果を見てみよう
IS曲線(モノの市場)とLM曲線(お金の市場)を1つのグラフに描くと、2つの曲線が交わる点ができます。この交点で、国全体の「国民所得」と「利子率」が決定される、と考えるのがIS-LM分析です。政府や日本銀行の経済政策が、この交点をどう動かすのかを分析します。
- 財政政策(政府の役割): 政府が公共事業を増やしたり、減税したりすること。
- 効果:IS曲線が右にシフトします。これにより国民所得は増えますが、同時にお金の需要が増えるため、利子率も上昇してしまいます。この利子率の上昇が、民間の投資を抑制してしまう現象を「クラウディング・アウト」と呼びます。
- 金融政策(日本銀行の役割): 日本銀行が世の中に出回るお金の量を増やしたり(金融緩和)、減らしたり(金融引き締め)すること。
- 効果:金融緩和を行うと、LM曲線が右にシフトします。これにより利子率は下がり、企業や個人がお金を借りやすくなるため、国民所得が増えます。
5. 労働市場の分析とAD-AS分析:物価と失業を考える
IS-LM分析は「物価が一定」という仮定がありましたが、現実には物価も変動します。そこで、物価の変動も考慮に入れた、より現実的なモデルがAD-AS分析です。
- 総需要(AD)曲線: 物価と国民所得の関係を示す右下がりの曲線です。物価が下落すると、手持ちのお金の価値が実質的に上がり、より多くのモノが買えるようになるため、国全体の需要が増えます。
- 総供給(AS)曲線: 物価と国民所得の関係を示す右上がりの曲線です。物価が上昇すると、企業は製品を高く売れるので儲かり、生産意欲が高まるため、国全体の供給が増えます。
- このAD曲線とAS曲線の交点で、現実の「物価水準」と「国民所得」が決まります。景気の変動、インフレ、デフレといった現象は、これらの曲線が何らかの要因で左右にシフトすることで説明されます。
6. 経済成長と国際マクロ経済学:グローバルな視点
- 経済成長: 長期的に国の生産能力が高まり、豊かになっていくことです。これは、AS曲線が技術革新や設備投資の増加などによって、継続的に右側へシフトしていくことで実現されます。
- 国際マクロ経済学: 貿易や国際的なお金の動き(資本移動)を考慮したマクロ経済学です。特に「マンデル=フレミングモデル」が重要で、これはIS-LM分析の国際版と考えると分かりやすいです。このモデルでは、「変動為替相場制(円ドルレートなどが日々変動する制度)」か「固定為替相場制」かによって、財政政策や金融政策の効果が全く異なってくることを分析します。例えば、変動相場制の日本では、金融緩和は円安を招いて輸出が増えるため効果が大きいですが、財政政策の効果は円高によって相殺されがちである、といったことが理論的に説明できます。
これらの理論を体系的に学ぶことで、日々のニュースで報じられる「日銀の金融政策」「政府の経済対策」「円安の影響」といった出来事が、なぜ、どのように私たちの生活や企業経営に影響を与えるのかを、深く理解できるようになります。
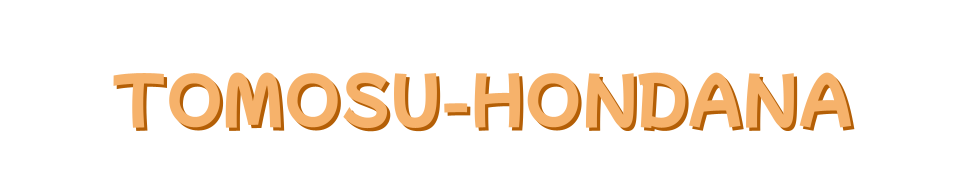
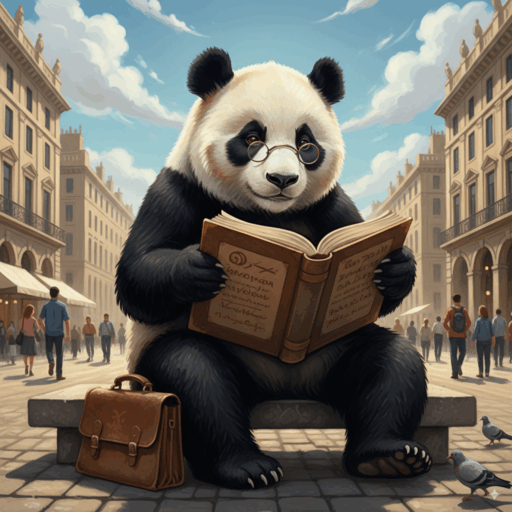
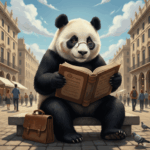

コメント